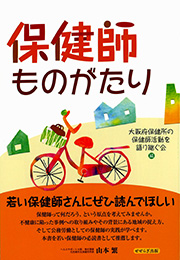
若い保健師さんに読んでほしい
保健師ものがたり
出版社:せせらぎ出版
著 者:大阪府保健所の保健師活動を語り継ぐ会
ジャンル
ドキュメンタリー/福祉/出産・子育て
キーワード
保健師/大阪府保健所/公衆衛生活動
閲覧タイプ
フィックス〈文字・画像サイズ固定〉|POD(プリント・オン・デマンド)
主な販売サイト
販売サイト(POD版)
内容紹介
若い保健師さんにぜひ読んでほしい。保健師って何だろうという原点を考えてみませんか。不健康に陥った事例への取り組みやその背景にある地域の捉え方、そして公務労働としての保健師の実践が学べます。本書を若い保健師の必読書として推薦します。(元尼崎市北保健所所長 山本 繁)
この本は大阪府の保健所で働いていた、また、今も働いている保健師たちの記録です。
保健師は150人(1957年)から、最高時348人(1981年)、現在は258人(2005年)となっています。保健所は20保健所2支所(1955年)から、最高時24保健所6支所(1980年)、現在は14保健所のみになりました。まさに社会の情勢を映し出した歴史そのものです。都市に人口が集中し、高度経済成長から公害の発生、革新府政の誕生、地方財政危機、行政改革、規制緩和による公的サービスの縮小から現在へつながっています。
私たちは、1994年、これらの歴史の中での苦しい思いを『保健婦のめ―見た・飛び込んだ・大阪のくらし―』(やどかり出版)にまとめ自費出版しました。そのなかで、保健師が頑張っているだけでは府民の生活は楽にならず、治療法もない難病も増えている実態を明らかにしています。府民の生活に「ぴったり寄り添う活動」の原稿を50人もの保健師が寄せています。当時、府の保健師が300名だったことを考えると、その活動の広さ、深さと意気込みを感じます。社会病理としての暮らしの実態から、そこに広がっている貧困は経済ばかりではなく、こころの貧困も生み出し、社会から孤立していく家族像をも鮮明にしています。保健師の公私の研究会も発展しました。
現在の格差社会は、家庭や地域をばらばらにし、人間性を破壊させ、多くの「いのち」を軽んじています。この生活の危機の中で「安全と安心の社会」がなくなり、一方で病院の倒産、保健所の統廃合が進んでいます。
これから、公衆衛生の道は途絶えるのでしょうか、またはまったく違う道になっていくのでしょうか。それとも、私たちの力でいきいきとした「公衆衛生活動」をとりもどすことができるのでしょうか。
保健師の「家庭訪問」は、専門職の中でも「公的に保障された」すばらしい機能です。この機能が与えられているのは、消防士、警察官など数少ない専門職だけです。
今回、保健師の有志で「家庭訪問」など、地域に出かけて行う「知らせる」「支える」「育てる」の活動をまとめてみました。自由参加の「大阪府保健所の保健師活動を語り継ぐ会」が編集する体験集のため、記述は部分的、主観的な部分もあり、テーマも歴史から健康課題まで多様ではありますが、「素人集団」の発行物としてお許しください。
ここに貫いているのは、いつの時代も「住民の困りごとに本気で向き合った」保健師の心意気そのものです。(「はじめに」より)
〈目 次〉
- はじめに
- 私の保健師活動
- K保健所での保健師活動
- 民主的な研修制度が実現した―保健師たちで研修制度を作った経過―
- ある保健所の経験―新しい業務評価を試みて―
- 保健師と母性保護活動
- 母性保護講師団活動
- 雑誌「世界」の原稿募集に応募して
- 家庭訪問記録より(「世界」1965年8月号掲載)
- 衛保会のことなど
- 森永ひ素ミルク事件の教訓
- 母子保健活動の変遷から学んだ保健師活動
- 路上出産
- 障害児の母とともに歩んで
- 子ども病院で働く保健師の役割―6年間の病院での実践をふりかえり―
- 私の大切にしてきたこと
- 府下いち早く虐待連絡会を始めた地域で
- 難病患者さんが安心して療養できる環境をつくる取り組み
- 難病―ALS患者会との出会い
- 死亡者調査のこと
- 「よい仕事がしたいから」労働組合
- 保健師の業務別専任制―大阪府保健所の現状のなかで―
- 編集後記

